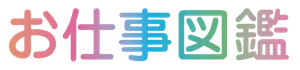前回、東京2020オリンピック金メダリストである渥美万奈さんが、現役引退後も「動けるコーチ」として全国を飛び回り、ソフトボールの普及に情熱を注ぐ「今の姿」をお届けしました。その活躍は、まさに順風満帆に見えるかもしれません。しかし、彼女のキャリアは、決して華やかなエリート街道ではありませんでした。むしろ、「挫折の連続」と表現する方が適切かもしれません。
今回は、金メダルという栄光を掴むまでの道のりで、彼女が経験した知られざる苦悩と葛藤に焦点を当てます。無名選手だった時代、周囲の期待と現実のギャップ、そして引退寸前まで追い込まれたスランプ。そのどん底で、彼女はいかにして立ち上がり、日本代表という夢を掴んだのでしょうか。
物心ついた頃にはボールを握っていた「野球一家」の宿命

渥美さんのソフトボール人生は、まさに「宿命」と呼ぶにふさわしい環境から始まりました。
「野球一家だったので、物心ついた時にはもうボールを握ってましたね。」
お父様がソフトボールの監督、お兄様も野球をしていたという環境で、彼女は自然とボールに親しみ、その才能を開花させていきます。中学時代までは、身近のソフトボール選手には自分より上手い選手はおらず、練習相手も女子では相手にならなかったため、男子の中に一人入っていたほど、順調に成長していきました。しかし、この「順調さ」が、後に彼女を苦しめる要因の一つとなります。
「フォームが綺麗すぎる」天才少女に訪れる早熟ゆえの挫折

中学時代、渥美さんはその才能ゆえに、ある種の「早熟の挫折」を経験します。
「小4の時ですね、その時はピッチャーで。バッテリー合宿っていうのに行ったんですよ。そこにいたコーチから。お前のフォームはキレイすぎるからもう伸びんよ、って言われて、それで何かポキッて折れた感じがありましたね」
彼女の「フォームが綺麗すぎる」という特徴が、技術指導の機会を奪うことにも繋がりました。指導者から見れば、完成されたフォームに見えるため、あえて口出しをする必要がないと判断されてしまったのです。結果として、彼女は自己流でプレーを続けることになり、これが後の伸び悩みに繋がってしまいます。
また渥美さんは、コーチが放ったたった一言が選手の心を折り、将来を閉ざしてしまう可能性も感じていたのです。
成績を残せなかった高校時代。無名選手だった渥美さん

高校時代、彼女が所属していたチームは、全国的な強豪校ではありませんでした。
この事実は、彼女が「エリート街道」とは無縁の、無名選手であったことを物語っています。唯一出場したのは「選抜大会」のみ。しかし、その大会もチームメイトがインフルエンザによって次々と倒れ棄権。渥美さんの活躍できる場面はありませんでした。
しかし、この「無名」であることが、彼女の不屈の精神を育む土壌となったのかもしれません。
「向こうのショート、いいよ」人生を変えた一言

そんな無名選手だった渥美さんに、運命の転機が訪れます。それは、高校2年生の時、練習試合で対戦した敵チームの監督からの何気ない一言でした。
「向こうのショート、いいよ」
この一言が、彼女の人生を大きく変えることになります。渥美さんは、その練習試合を見に来ていた実業団のスカウトの目に留まったのです。元々そのスカウトマンは、敵チームのエースの視察に来ていました。その子はインハイ優勝チームのピッチャー。当時のソフトボール界で知らない人はいないほど注目されていました。
しかし、敵チームである筈の監督が、渥美さんを指差し推薦したのです。この言葉をきっかけに、彼女の実業団チームへの入団が決まります。
たった一言が、一人の選手の未来を切り開く。このエピソードは、「誰かの言葉が人生を変える」という、このメディアのコンセプトを体現していると感じました。
同じポジションの同期は6人。「その他大勢」からのスタート
鳴り物入りで実業団に入団したわけではなかった彼女を待っていたのは、同じポジションに6人もの同期がいるという、厳しい競争環境でした。
入団後もすぐにレギュラーを掴むことはできず、1年目、2年目でレギュラー入りしていく同期を横目に、3年目までベンチという苦しい時期を過ごします。周りの選手が次々と日本代表に選ばれていく中で、彼女は「その他大勢」の一人として、焦燥感と戦い続けました。
しかし、この「遅咲き」の経験こそが、彼女の粘り強さと、チャンスを逃さない集中力を養ったと言えるでしょう。
突然ボールが捕れなくなった…引退寸前のスランプと盟友との出会い

レギュラーを掴み、日本代表に選ばれ、世界選手権でのメダルも獲得するほどになった渥美さんですが、さらなる試練が待ち受けていました。それは、2016年の世界選手権から帰国した直後に襲った深刻なスランプです。
「急に取れなくなっちゃいました。ボールが。このワンバンしてくる打球が急に取れなくなっちゃって」
守備の要、ショートを守る彼女にとって、ボールが捕れないという事態は、まさに選手生命の危機でした。一度の試合でのエラーが多くなり、渥美さんの脳裏には引退の二文字が浮かびます。「もう限界かなぁ…」力なく呟く彼女の表情には寂しさが溢れていました。
そんな時、渥美さんはとあることに気付きます。その年に移籍してきたとあるチームメイトが、やけに自分に注意をしてくるのです。
幼少期から周囲と比べ物にならないほどの実力を持っていた渥美さん、そのチームメイトほど、執拗に、丁寧に声をかけられるという経験は初めてだった。勇気を出して「ソフトボールをもう一回、一から教えてください」と頼み込んだ夜9時。真っ暗な公園で始まった練習が、彼女の「第二のソフトボール人生」の始まりとなったのです。
誰かから注意をされると、誰しも落ち込み、時には反発してしまうこともあるでしょう。しかし、「言われるうちが花」という言葉があるように、その注意が不条理なものか、その人の愛からくるものなのかを養う「選球眼」が、怒られる機会が激減している現代に必要なものかもしれません。
【次回予告】

どん底のスランプから、盟友との出会いを経て立ち直った渥美さん。しかし、彼女の挑戦は、金メダル獲得で終わりではありませんでした。
現役引退後、彼女が目指した「動けるコーチ」という道。それは、単なるセカンドキャリアではなく、ソフトボール界の未来を変えるという壮大な夢へと繋がっていました。
次回は、渥美さんが描く「未来への展望」と、スポーツ界に残る古い常識への「改革のメッセージ」に迫ります。